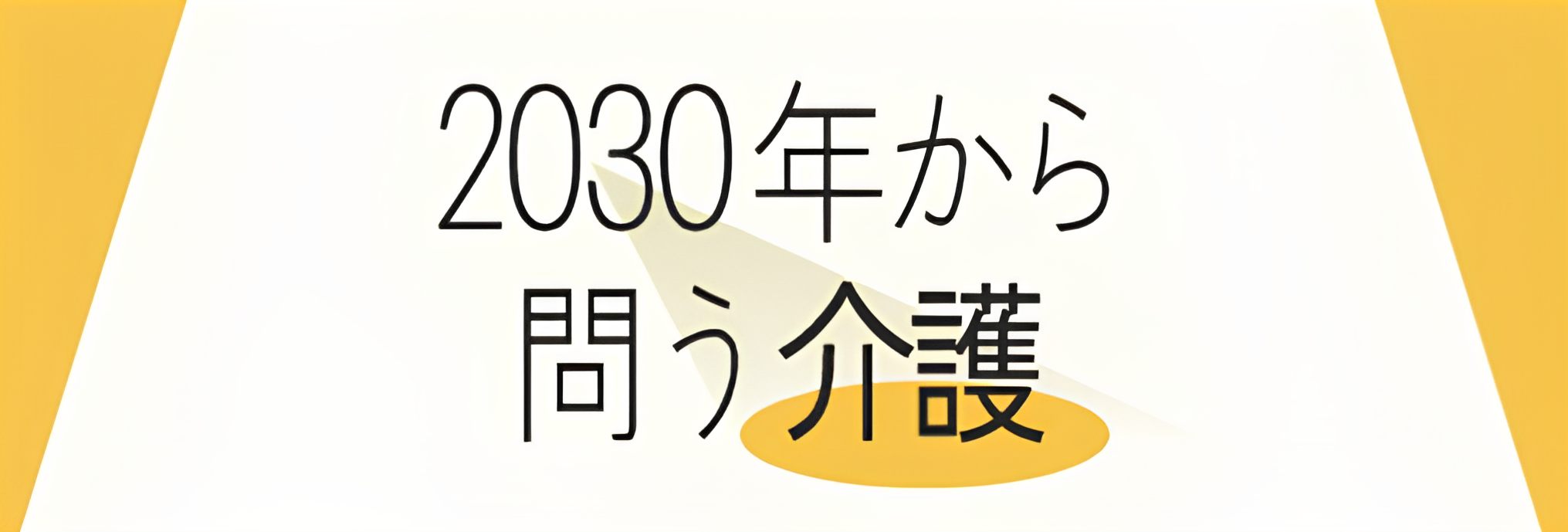こんにちは!今回は「介護施設における人員配置基準」について解説します。
介護施設には、利用者が安心して生活できるように、厚生労働省が定めた人員配置基準が設けられています。
この基準を守ることで、施設側は適切なサービスを提供し、利用者にとっても安全で安心な環境が保たれます。具体的にはどのような基準があるのか、見ていきましょう✊️
また、人員配置基準を遵守しているかどうかは、自治体による運営指導で確認されます。その運営指導の目的や流れもあわせて見ていきたいと思います!

介護施設の代表的な人員配置基準は?
介護施設における人員配置基準は、厚生労働省により定められており、各施設が入居者や利用者に対して適切なサービスを提供するための最低限の人数を規定しています。それぞれの施設で求められる人員配置基準は異なりますが、共通して「利用者が安心して生活できる環境」を整えることが目的です。
それでは、以下で介護施設ごとの具体的な基準を見ていきたいと思います。
特別養護老人ホーム(特養)
| 職種 | 配置基準 |
| 管理者 | 1以上 |
|
介護職員 |
3:1以上(入居者3人に対して1名以上) |
| 生活相談員 | 100:1以上 |
| 機能訓練指導員 | 1以上 |
| 介護支援専門員 | 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする) |
| 栄養士 |
1以上 ※入所定員40人未満の場合、他の社 会福祉施設の栄養士との連携により効 果的な運営ができ、入所者の処遇に支 障がない場合は置かなくてもよい。 |
夜勤体制について
・夜勤時の人員配置については、施設の規模や入居者の状況に応じて適切な配置を確保します。
・各階ごとに最低1名の配置が望ましいとされていますが、基準以上の人員を配置することでサービスの質向上が期待されます。
参考:厚生労働省「介護老人福祉施設の基準(p.2)」
介護老人保健施設(老健)
| 職種 | 配置基準 |
| 医師 | 常勤1以上、100:1以上 |
|
介護職員 |
3:1以上(入居者3人に対して1名以上)、うち看護師は7分の2程度を確保 |
|
支援相談員 |
100:1以上(入居者100名までは1、それを超えると追加) |
|
理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士 |
100:1以上 |
| 介護支援専門員 |
100:1以上 |
| 栄養士 |
入所定員100以上の場合、1以上 |
夜勤体制について
・夜間及び深夜は2ユニットごとに1人以上の 介護職員又は看護職員を配置が必要。
参考:厚生労働省「介護老人保健施設の基準(p.2)」
認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
| 職種 | 配置基準 |
| 管理者 | 3年以上認知症の介護従事経験があり、厚生労働大臣が定める研修を修了した者が常勤専従 |
| 介護職員 |
[日中]3:1以上(常勤換算方法) |
| 計画作成担当者 | ユニット毎に1(最低1人は介護支援専門員、ユニット間の兼務は不可) |
夜勤体制について
・夜間帯は1ユニット(5~9人の利用者)につき最低1人の職員が必要。複数ユニットある場合、夜間対応のスタッフが巡回する形も可能です。
参考:厚生労働省「認知症対応型共同生活介護の基準(p.1)」
グループホーム(共同生活援助)
| 職種 | 配置基準 |
| 世話人 |
6:1以上(日中サービス支援型は利用者5人に1人以上) |
| 生活支援員 |
利用者の障害支援区分(★2) に応じて常勤換算でイ~ニの合計数以上 |
| サービス管理責任者 |
30:1以上(利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上) |
| 管理者 |
1以上(常勤で管理業務に従事、支障がない場合は他の職務との兼務可) |
夜勤体制(夜間支援)について
・日中サービス支援型は 共同生活住居ごとに1人以上の夜勤職員の配置が必要(宿直不可)。
・介護サービス包括型及び外部サービス利用型は 任意。配置すると加算対象になる。
参考:厚生労働省「グループホーム(共同生活援助)の基準(p.24)」
デイサービス(通所介護)
| 職種 | 配置基準 |
| 介護職員 |
15:1以上(利用者16人以上は5人増ごとに1追加) |
| 看護職員 |
単位ごとに専従で1以上 |
| 生活相談員 (社会福祉士等) |
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上 |
| 機能訓練指導員 |
1以上(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師) |
夜勤体制について
・通所型のサービスのため、夜間の人員配置基準はありません。
参考:厚生労働省「通所介護の基準(p.2)」
小規模多機能型居宅介護
| 職種 | 配置基準 |
| 介護従業者 (通いサービス) |
3:1以上(常勤換算方法) |
| 介護従業者 (訪問サービス) |
1以上(常勤換算方法) |
| 看護職員 |
介護従業者のうち1以上 |
| 介護支援専門員 |
1以上(介護支援専門員で、小規模多機能型サー ビス等計画作成担当者研修を修了した者) |
夜勤体制について
・夜勤職員:時間帯を通じて1以上(宿泊利用者がいない場 合、置かないことができる。)
・宿直職員:時間帯を通じて1以上(随時の訪問サービス に支障がない体制が整備されている場合、必 ずしも事業所内で宿直する必要はない。)
参考:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護の基準(p.3)」
訪問介護
| 職種 | 配置基準 |
| 訪問介護員 | 2.5以上(常勤換算方法) |
| サービス提供責任者 |
40:1以上 (原則として常勤専従の者であるが、一部非常勤職員でも可) |
| 管理者 |
常勤専従で1 |
夜勤体制について
・夜間対応型訪問介護は、夜間に対応可能な人員を確保する。
参考:厚生労働省「訪問介護の基準(p.6)」
介護事業の運営指導について
介護事業の運営指導とは、事業所が介護保険制度に基づき適切な運営を行い、利用者に安心で質の高いサービスを提供するために自治体が実施する指導や監査のことです。この取り組みは、法令遵守やサービスの質の向上、不適切な請求の防止を目的としています。
以下に、運営指導の目的や流れ、準備について詳細に解説します。

運営指導の目的
運営指導には、介護事業者が適切なサービス提供を行うための以下の目的があります。
- 法令遵守の確保:介護保険法や関連規則に基づき、事業所が適正な運営を行っているかを確認します。
- サービス品質の向上:利用者に対して適切で安全なサービスを保証するため、記録や運営状況を点検します。
- 不正や不適切な請求の防止:介護報酬の不正請求や過剰請求を防ぐことで、公平で健全な制度運営を確保します。
運営指導の流れ
運営指導は以下のような流れで進められます。
- 事前通知:自治体から事業所へ、指導日程や提出書類についての通知があります。
- 現地調査:自治体職員が事業所を訪問し、記録や運営状況、施設の状況を確認します。
- ヒアリング:管理者や担当職員から、業務体制やサービス提供方法について聞き取りを行います。
- 指導結果の通知:指摘事項や改善が必要な箇所について報告があり、事業所は必要に応じて改善計画を提出します。
主な指導内容
運営指導で確認される主な項目は以下の通りです。
- 人員配置基準:スタッフの人数や資格が基準を満たしているか。
- 介護報酬の請求内容:報酬請求が適正であり、不正や過剰請求がないか。
- 記録や報告書類:ケアプランやサービス提供記録が正確かつ適切に管理されているか。
- サービス内容の妥当性:利用者のニーズに合った適切なサービス提供が行われているか。
- 運営体制の確認:利用者の苦情対応、個人情報の保護、緊急時対応などが整備されているか。
指導後の対応
指導の結果、不適切な運営が確認された場合、以下のような対応が求められます。
- 改善計画の提出:指摘された問題点を解決するための具体的な計画を作成します。
- 再指導の可能性:必要に応じて、改善状況を確認する再指導や監査が実施されることがあります。
- 行政処分のリスク:重大な違反がある場合、事業停止や指定取り消しなどの行政処分が行われる可能性があります。
運営指導への備え
事業所が運営指導に備えるためには、日常的な体制の整備が重要です:
- 記録の管理:介護記録、勤務表、請求書類などを正確に整理・保管します。
- 法令の理解と遵守:全職員が介護保険法や関連規則を理解し、適切に運用するよう徹底します。
- 内部監査の実施:定期的に自己点検を行い、運営状況を把握する。
- 職員研修の充実:法改正や運営基準の変化に対応するための教育を行う。
介護事業の運営指導は、事業所が法令を遵守し、利用者に安心・安全なサービスを提供するために重要な取り組みです。日常的に記録や体制を整備することで、スムーズな対応が可能となります。また、指導を事業運営の改善につなげる姿勢を持つことが、利用者の満足度向上や信頼性の確保につながります。
運営指導でよく見られる指摘事項(過去事例より)
人員配置基準の不遵守
指摘内容:職員数や資格要件が基準を満たしていない。
- 事例1:特養で3:1の介護職員配置基準が不足し、自治体から改善指導を受けた。採用計画が遅れたことが原因。
- 事例2:生活相談員が常勤ではなく、非常勤で対応していたため基準を満たさないと判断された。
原因:採用難やシフト調整の不備。
改善策:シフト管理の見直しと資格取得支援などの職員育成。
記録の不備
指摘内容:ケアプランやサービス提供記録が不適切または不整備。
- 事例1:訪問介護で記録時間と実際のサービス時間が一致せず、自治体から虚偽の疑いを指摘された。
- 事例2:サービス提供記録が未記入の状態が複数発見され、職員間で記録のルールが共有されていないことが判明。
原因:記録ルールの周知不足や記録管理の手間を省いた結果。
改善策:定期的な記録の点検、記録ルールの徹底。
介護報酬の不正請求または過剰請求
指摘内容:実際に提供していないサービスに対して請求を行う。
- 事例1:デイサービスで短時間利用の利用者を長時間利用として請求し、不正請求と判断された。
- 事例2:訪問介護でサービスを提供していない日に請求が行われていたことが調査で判明。
原因:事務処理のミス、または不正意図。
改善策:職員への研修を徹底し、適正な請求ルールを運用。
利用者への説明や同意の不足
指摘内容:契約変更やサービス内容の説明が不十分で、同意が得られていない。
- 事例1:ケアプラン変更時に家族の同意を取らず、トラブルとなった。
- 事例2:サービス開始時に重要事項説明書が未交付だったことが指摘された。
原因:契約時の説明の簡略化、家族とのコミュニケーション不足。
改善策:契約や変更内容の説明を記録し、利用者・家族の署名を得る。
個人情報保護の不備
指摘内容:利用者情報の管理が杜撰。
- 事例1:利用者の記録を無施錠のデスクに放置し、第三者が容易にアクセスできる状況だった。
- 事例2:電子データが暗号化されておらず、外部からのアクセスリスクが指摘された。
原因:職員の意識不足や情報管理システムの不整備。
改善策:個人情報保護規程の策定と職員教育の強化。
苦情対応体制の不備
指摘内容:苦情受付や対応の記録が適切に行われていない。
- 事例1:家族からの苦情が未対応のまま放置され、自治体から指摘を受けた。
- 事例2:苦情対応の履歴が全く残っておらず、再発防止策が講じられていなかった。
原因:苦情処理フローの欠如、または職員の認識不足。
改善策:苦情受付の窓口を明確化し、記録・共有ルールを整備。
緊急時対応マニュアルの不備
指摘内容:災害や事故発生時の対応体制が不十分。
- 事例1:避難訓練が未実施で、職員が緊急時の手順を理解していないことが発覚。
- 事例2:緊急時の連絡体制が整備されておらず、家族への連絡が遅れたケース。
原因:マニュアルの整備が遅れている、または訓練不足。
改善策:定期的な訓練実施と記録の保管。
法改正への対応不足
指摘内容:最新の法改正や報酬改定に基づいた運営が行われていない。
- 事例1:介護報酬改定後も旧基準で請求を行い、不適切な運営と判断された。
- 事例2:改定で新たに義務付けられた書類の整備が遅れており、自治体から改善命令を受けた。
原因:法改正情報の把握不足。
改善策:定期的な研修会への参加、情報収集の仕組みを作る。
介護事業の運営指導では、人員配置、記録管理、適正請求、法令遵守が特に重要視されます。事業所は日々の運営を見直し、内部点検や研修を通じて改善を図ることで指摘を未然に防ぐことが可能です。また、指導内容を前向きに捉え、サービスの質向上に活用する姿勢が求められます。