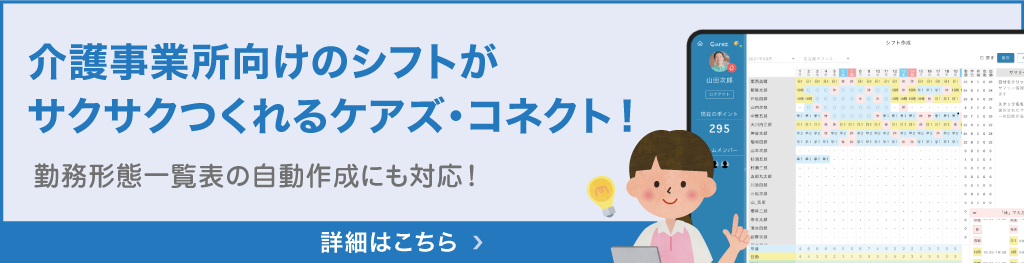介護業界では、シフト制や夜勤が多いことから、勤怠管理が複雑になりがちです。
不適切な勤怠管理は労務トラブルを引き起こし、職場環境の悪化や離職の上昇につながります。本記事では、実際に発生した勤怠トラブル事例をもとに、その対策を考えていきます。

事例1:夜勤・送迎ドライバーの勤務による勤怠管理の複雑化
ある介護老人保健施設では、日勤・夜勤のほかに、送迎ドライバーの職員が1日2時間ずつ2回勤務するシフトを採用していました。
しかし、従来使用していた勤怠管理ソフトでは「1日1回の出退勤打刻」しか対応しておらず、2回目の勤務が記録されない問題が発生。
結果、勤務時間が実際より短く記録され、給与計算にも影響が出ていました。
管理者が毎日打刻内容を目視で確認し、修正を手入力していたため、月末の勤怠締め作業に多大な時間と労力がかかっていました。
対策
- 複数回勤務に対応したクラウド型勤怠管理システムの導入
- 「分割勤務(中抜け対応)」や「シフトパターンの自由設計」が可能なシステムを選定
- モバイル対応で、送迎先など外出先からの打刻にも対応
事例2:夜勤スタッフの時間超過と申送りの抜け
あるグループホームでは、夜勤スタッフが定時よりも早く出勤し、翌朝は延長して勤務(退勤)することがありました。本来のシフトでは「16:00〜翌10:00」だが、実際は「15:15〜10:30」とバラつきが発生し、時間外労働の申請漏れや、給与計算との不一致が発生していました。
紙のタイムカードでは、スタッフ本人が記録ミスをすることもあり、また管理者側もタイムリーに確認できず、超過分の申請漏れや未払い問題に発展するリスクがありました。
対策
- リアルタイムで出退勤状況を確認できる勤怠システムの導入
- 夜勤シフト専用の勤務パターンを設定し、出勤時間の「早出・遅れ」を自動検知
- 勤怠情報と給与計算を自動連携し、手動修正を削減
事例3:複雑な手当計算がもたらす給与計算ミス
介護施設では、職員の働き方が多様であることから、給与計算には、夜勤手当や残業手当などの様々な手当の反映が必要となります。具体的には「夜勤手当・早朝手当・休日勤務手当」「勤務時間に応じた支給額の変動」。これらの手当は、勤務時間やシフトのパターンに応じて細かく支給条件が異なるため、
毎月の給与計算においては、その都度、個別に確認・計算を行う必要があり、非常に時間を要します。
また、計算作業の多くを手作業で行っていたことから、入力ミスや計算ミスが発生し、給与支給後に内容の修正や職員への説明対応が必要になるケースも発生していました。
対策
- 勤怠管理システムと給与計算ソフトを連携し、計算ミスを防止
- 手当や残業時間を自動集計し、管理者の負担を軽減
- 一括処理機能を活用し、給与計算の効率化を図る
事例4:紙や手作業によるヒューマンエラー
ある介護施設では、長年「紙のタイムカード」「出勤簿」「Excel表」などを使って、出退勤や労働時間の集計を行ってきました。
しかし、これらの方法には「手書きによる記入ミスや記録漏れ」「手計算の集計ミスや二重入力」「勤怠状況をリアルタイムに把握できない」「月末の締め作業に非常に時間がかかる」といった課題がありました。
特に、変則シフトが多い現場では、手作業での集計が煩雑になり、給与計算とのズレや職員からの問合せが絶えないといった問題が見受けられます。
対策
- クラウド型の勤怠管理システムで集計業を自動化
- 打刻ミスや打刻漏れアラート機能に対応したものを整備
事例5:システムに不慣れな職員による混乱
業務効率化や労務管理の正確性を高める目的で、勤怠管理システムの導入が進んでいます。
新たに勤怠管理システムを導入したある介護施設では、思わぬ壁に直面しました。そこには、ITに不慣れな職員が多いという介護現場の事情がありました。
導入当初、管理者は「これで勤怠管理が正確になり、給与計算も効率化良くなる」と期待していました。ところが、実際にはシステムを使用する職員からは、「画面の見方がわからない」「そもそもスマホやPCの操作に慣れていない」といった戸惑いや不安の声が多くあがりました。
その結果、勤怠記録の不備が頻発する事態となってしまい、現場の混乱を招く結果となってしまったのです。
- 導入初期は職員説明会や操作体験会を実施し、実際に触れながら覚えてもらう
- 操作がシンプルで視認性の高いUI(ユーザーインターフェースを持つシステムを選定
- 打刻ミスがあっても管理者が柔軟に修正できる(代理で登録できる)機能があるシステムを選定
事例6:サービス残業問題(空白の時間がある)
介護施設では、職員が高い責任感を持って業務に取り組んでおり、定時を過ぎても利用者対応や記録業務を続けるといった場面が少なくありません。
しかし、その一方で、残業申請が適切に行われていないという問題が見られるケースがあります。
ある施設では、職員が定時を過ぎて業務を継続しているにもかかわらず、残業申請が未提出のままになっていたことが発覚しました。
この結果、「定時で退勤した」と記録されてしまい実際に働いた時間と記録上の労働時間にズレが生じている状態となっていました。このような状況が続くと、サービス残業と見なされるリスクが高まり、労働基準監督署による監査が入った場合、指摘を受ける可能性があるとの懸念が管理者から挙がっていました。
対策
- 残業発生時に自動通知されるアラート機能の活用
- シフトと打刻に乖離があった場合に乖離理由を登録できる機能を導入
事例7:「入職日基準」の有給付与で管理が煩雑に…
ある介護施設では、有給休暇を職員の入職日を基準にして個別に付与していました。この運用自体は法令に沿ったものですが、職員が増えるに従って「職員ごとに有給の付与日・残日数・消化状況がバラバラ」「誰にいつ付与したかの確認作業に時間がかかる」「有給残数をもとにした休暇承認でミスが発生」というように管理が非常に煩雑になり、管理負担も増えていました。
その結果、管理者は毎月の勤怠締め処理や有給管理のたびに時間を要していました。
対策
- 入職日を登録するだけで、有給の自動付与・消化履歴の管理が可能な勤怠システムを導入
- 職員ごとの残日数がリアルタイムで把握できる画面を用意
- 有給取得状況も勤怠管理システム上で一目で確認できるものを選定
事例8:事業所を兼務する職員の勤怠管理が煩雑に
ある社会福祉法人が運営する施設では、特別養護老人ホームとデイサービスを併設しており、職員が両方の部署を兼務して勤務していました。
しかし、従来の勤怠管理ソフトでは「1人の職員が複数のシフト表に所属する設定」ができず、シフト表作成時に「特養」と「デイサービス」の勤務予定を別々に管理する必要がありました。
その結果、同じ職員が両施設で重複して勤務予定に入ってしまうケースが発生し、人員が足りない時間帯が生じるといったトラブルがありました。
また、タイムレコーダーを使用しているとある施設では兼務している職員のデータをそれぞれ確認する必要があり、月末の勤怠締め作業で確認や修正に多くの時間がかかっていました。
対策
- 特養とデイサービスなど複数のシフト表への所属が可能な勤怠管理システムの導入
- 部署をまたいでも勤務時間は自動集計し、給与計算や勤怠締めの手間を軽減
事例9:勤務形態一覧表が作成できず、監査前に慌てて対応
ある介護施設では、勤務形態一覧表を出力する機能がない勤怠管理方法を採用していました。
そのため、実地指導や申請書類などで勤務実績を提出する際には、毎回手作業で勤怠データを確認し勤務形態一覧表を作成する必要があり大きな負担となっていました。
特に、急な監査対応時には、限られた時間内で資料を整える必要があり、確認作業や修正に追われ、大きな負担となっていました。
対策
- 勤務形態ごとに勤務時間や人数を一覧化して出力できる介護業界に特化した勤怠管理システムを導入
- ボタン一つで必要な集計表が出力できるものを選定し、監査対応時の資料作成負担を大幅軽減
- 集計データは履歴として保管され、再提出や過去確認にもスムーズに対応できるものを選定
事例10:転記や電卓計算による常勤換算の計算ミス
ある介護施設では、監査や加算要件確認の際に「勤務形態一覧表」の提出を求められていました。
この一覧表は、職員の雇用区分(常勤・非常勤・パートなど)と、実働時間をもとに「常勤換算数」を計算し記載する必要があります。
しかし、勤怠データがシステム上で一覧表として出力できず、毎月Excelへ手入力して作成していたため、大きな手間と時間がかかっていました。
特に短時間勤務の職員、事業所や職務を兼務している職員が多い事業所では、勤務実績を確認しながら計算ミスや転記ミスを防ぐため何度もチェックが必要になり、計算のやり直しや再作成を繰り返す状況が続いていました。
対策
- 勤怠管理システムから「常勤換算数」がワンクリックで出力、計算可能な機能を活用
- 勤務実績に基づき、常勤換算数も自動計算され、転記ミスや集計漏れを防止
介護業界における勤怠管理の問題は、現場の負担や労務トラブルの原因となります。
しかし、適切な勤怠管理システムを導入することで、これらの問題を未然に防ぐことが可能です。
介護施設の運営を円滑にし、スタッフの働きやすさを向上させるためにも、
介護事業所特化の勤怠管理システムの導入を検討してみませんか?